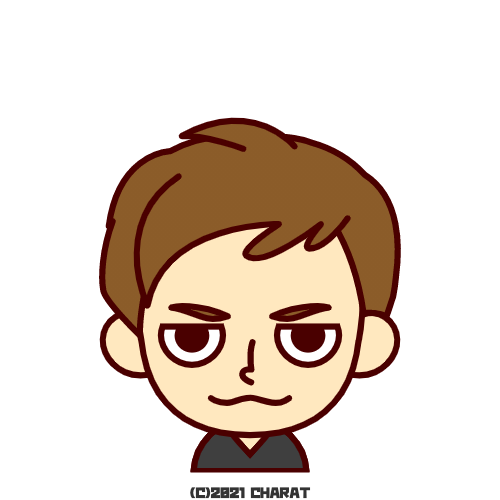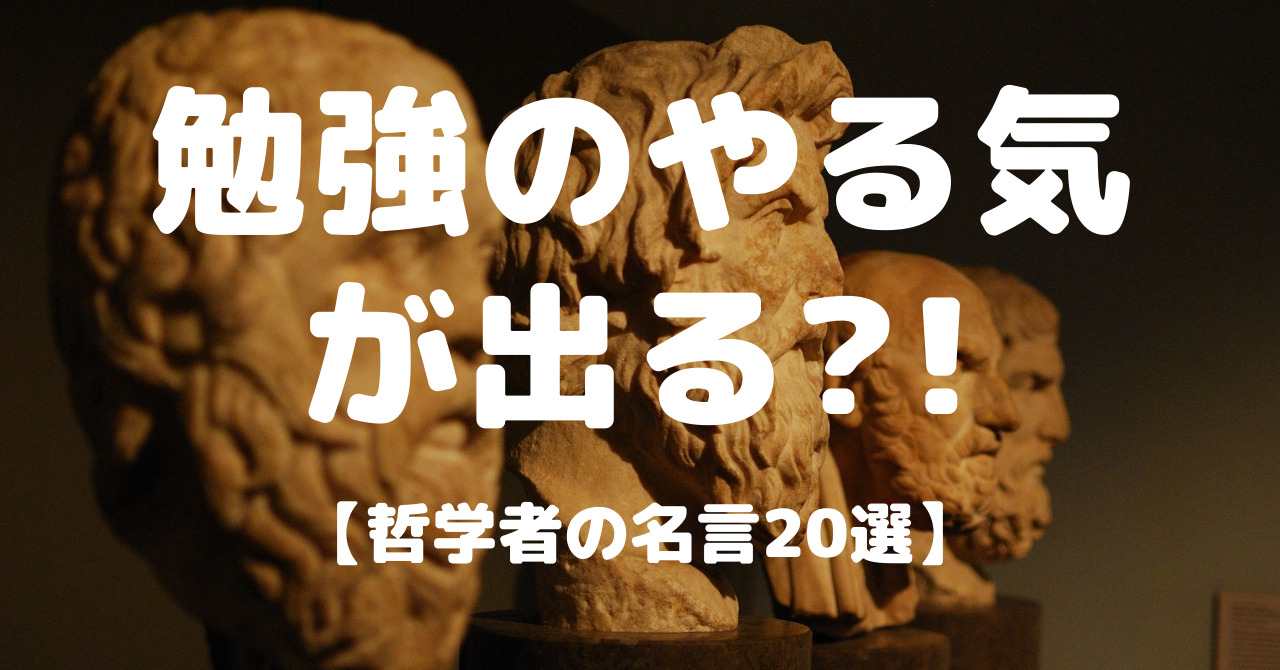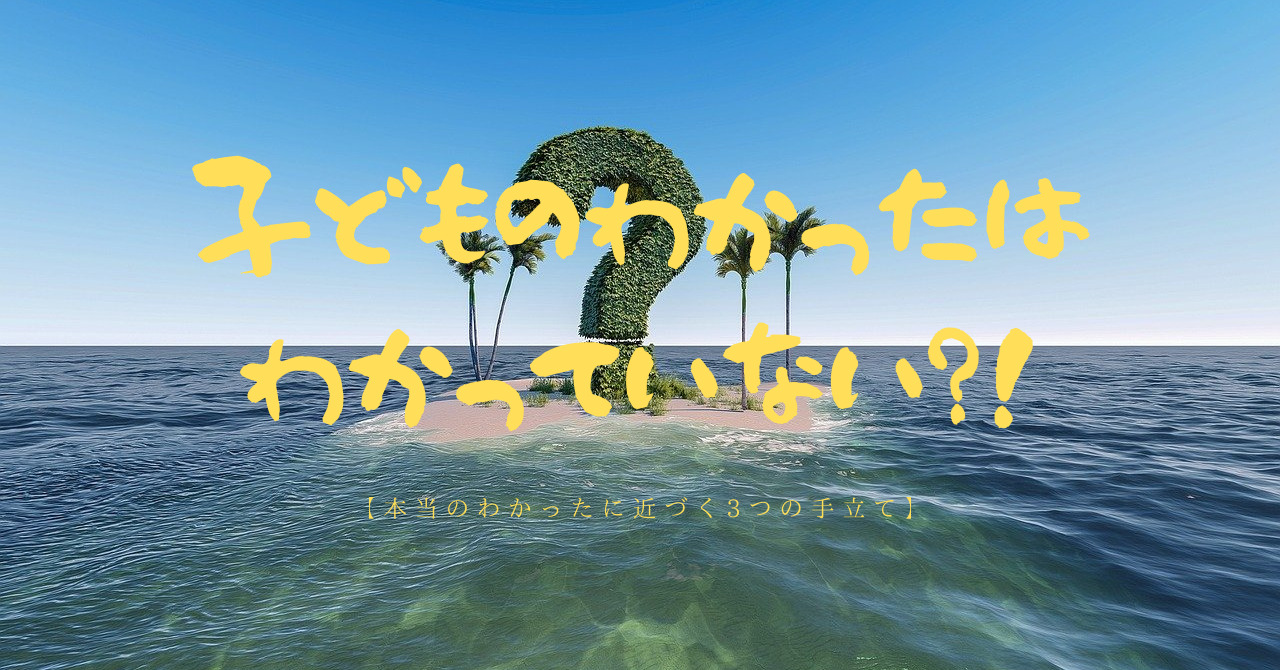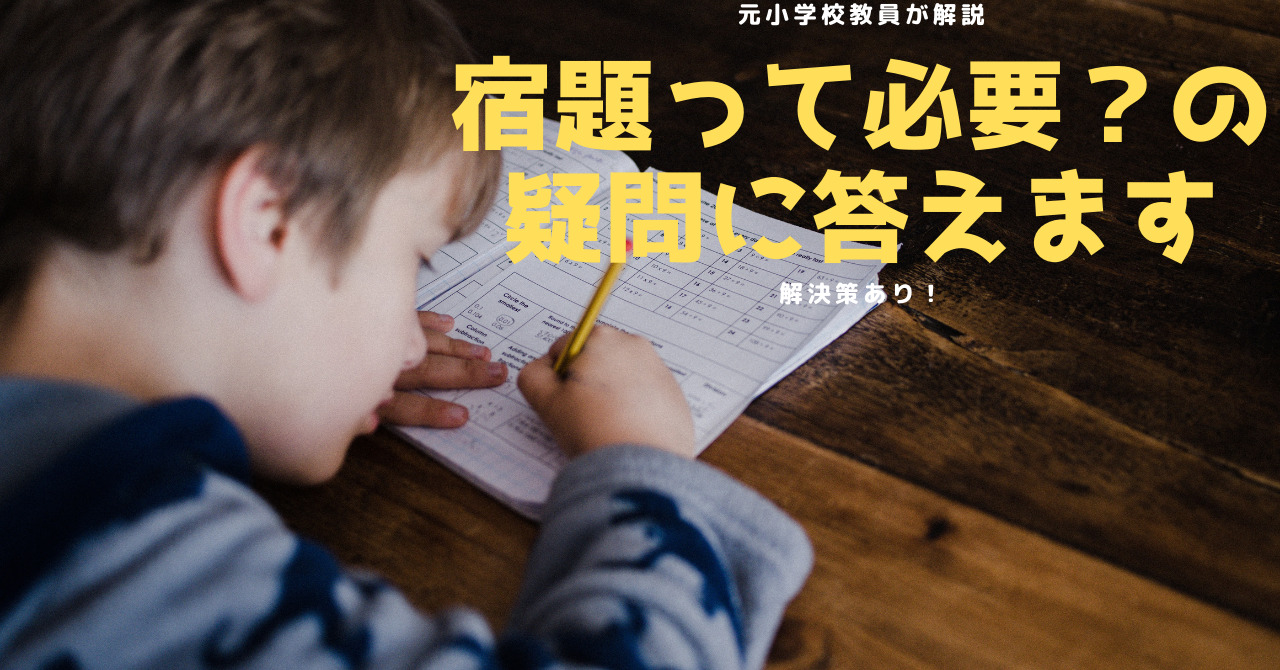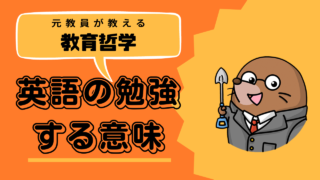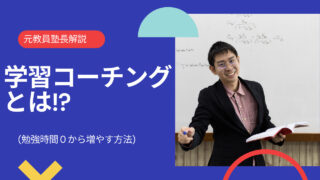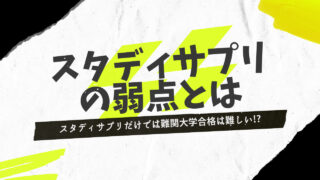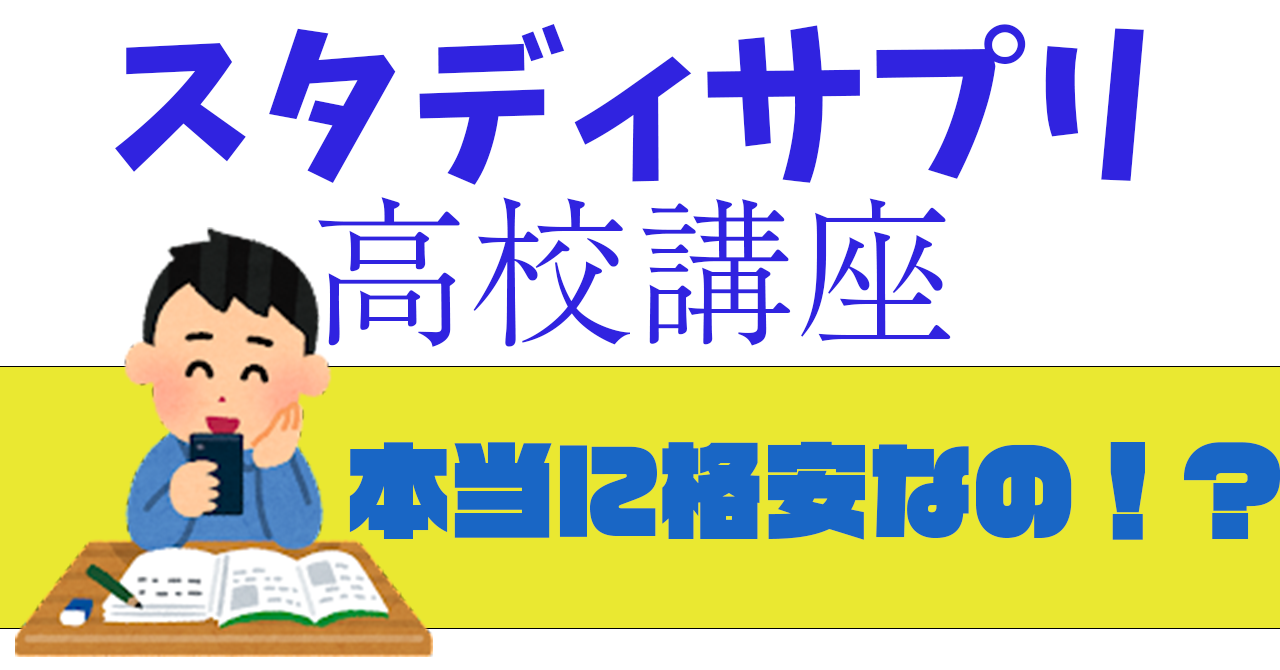「子どもの勉強嫌いを治したい!」
といったご相談をよく耳にします。
多くの保護者は子育ての仕方を
学んだことがありません。
そのため、
「勉強しなさい!」と言っているだけの方も
多いのではないでしょうか?
しかし、ただ「勉強しなさい」とだけ伝えても
子どもの勉強嫌いは治りません。
そこでこの記事では、
勉強嫌いを克服する方法について
ご紹介します。
子どもが勉強嫌いになる原因や
効果的な接し方などについても
解説していますので、ぜひご参考にしてください。
- 子どもが勉強せず困っている方
- 子どもに勉強してほしいと願っている方
- 子どもの指導方法がわからない方
子どもが勉強嫌いになる原因
子どもが勉強嫌いになる原因は
いくつかあります。
まずは原因を分析し、
それぞれ異なる対策を行うことが大切です。
子どもが勉強嫌いになる原因は
おもに下記の4つが挙げられます。
- 勉強内容分からないから
- おもしろくないから
- 勉強の仕方が分からないから
- 勉強する意味が分からないから
勉強内容が分からないから
勉強を嫌いになるシンプルな原因として、
「勉強内容が分からないから」があります。
勉強内容が分かっていないと、
問題を解けないため、
勉強に嫌気をさすのも当然です。
中には「自分は勉強ができない」と
思いこんでいる方もいるでしょう。
しかし、一から復習をしていくことで、
この問題を解決できることもあります。
まずはどこが理解できていないのか
把握することが大切です。
おもしろくないから
2つ目の原因は、
「勉強内容がおもしろくないから」です。
受験や進学のために仕方なく勉強していると、
勉強はただの作業にしかなりません。
イヤイヤ作業を続けていれば、
勉強を嫌いになるのは当たり前です。
嫌でも勉強しなければならないのであれば、
勉強におもしろみを見つける努力をしましょう。
勉強の仕方が分からないから
3つ目の原因は、
「勉強の仕方が分からないから」です。
勉強には、「効率的に暗記する方法」や
「自分に合う勉強法」というものがあります。
しかし、これらの勉強法を知らなければ、
頑張っても成績は上がりにくく、
達成感を味わえません。
正しい勉強法を知れば、
勉強への嫌悪感をなくせるでしょう。
勉強する意味が分からないから
4つ目の原因は、
「勉強する意味が分からないから」です。
勉強する意味が分からない人の共通点として、
「目標が明確にない」というものがあります。
・「志望校合格」
・「テストで80点以上取る」など、
勉強をする目標を見つけることは大切です。
また、その目標を達成したら
どんな良いことがあるか考えておくと、
勉強する意味を見つけられるでしょう。
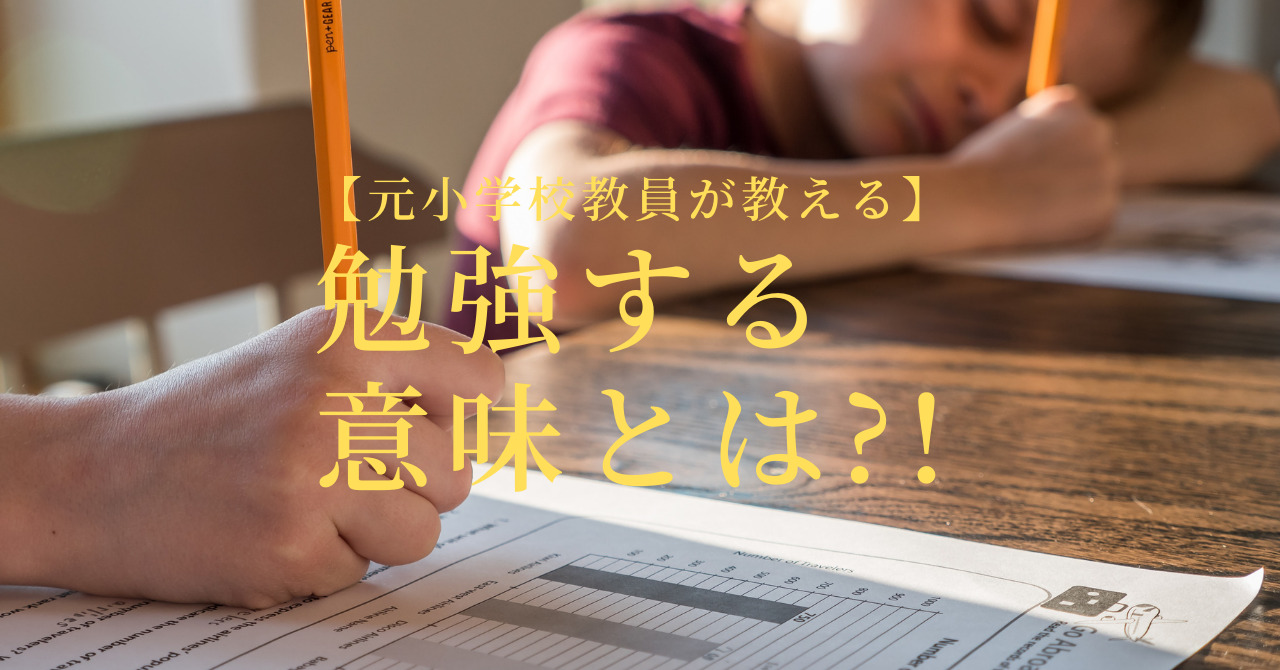
勉強嫌いを克服する方法
勉強嫌いになる原因が把握できれば、
次は勉強嫌いを克服しましょう。
勉強嫌いになる原因それぞれの克服法を
解説していますので、ぜひご参考にしてください。
- 原因:分からないから→スモールステップで進める
- 原因:おもしろくないから→興味関心のある内容から勉強する
- 原因:勉強の仕方が分からないから→効果的な勉強法を知る
- 原因:勉強する意味が分からないから→勉強して達成したい目標を設定する
スモールステップで進める
勉強嫌いになる原因が
「勉強内容が分からないから」である方は、
スモールステップで勉強を進めましょう。
まずは達成感を味わうことが必要です。
達成感を味わうためには、
今自分ができることから始めることが大切。
特に、積み上げの教科と言われる
英語や算数・数学は、分からない問題があれば
その前の範囲の内容を
理解できていない可能性が考えられます。
この場合、理解できていない内容を
ほったらかしにしておくと、
どんどん分からなくなってしまいます。
例えば、たし算ができていない状態で
かけ算を理解することはできません。
たし算を理解し、慣れてきたところで
次のかけ算に進めます。
しかし、たし算を理解できていない状態でも
学校はかけ算の授業に進むことがあります。
これは集団授業を行う学校であれば
仕方のないことです。
しかし、そのままでは
かけ算が全く分からなくなってしまうので
勉強を嫌いになってしまいます。
もしたし算を理解できていない状態で
かけ算の授業に入った場合、
家でまずたし算を勉強することがおすすめです。
学校に合わせて焦らることなく、
子どものペースで少しずつ頑張っていきましょう。
興味関心のある内容から勉強する
勉強はやらされていると感じると、
おもしろみを感じないことが多いです。
これは仕方ありません。
そこで、まずは
「やらされている感」を無くす必要があります。
子ども自ら「勉強をしたい!」と
思ってもらうためには、
子どもが興味関心のある内容や教材を
使用することが大切です。
例えば、動物が好きなお子さまの場合、
動物を調べることから
知識を増やしていきましょう。
ゲームが好きな子だと、
勉強をゲーム化して
興味関心を持たせることも1つの手段です。
ゲームでは、ボスを倒すために
様々な攻略法を使います。
武器を強化したり、
レベルを上げたりもするでしょう。
これを勉強に置き換えて考えます。
「ボス(勉強の目標)」を倒すために
「武器の装備(知識)」や
「レベル上げ(勉強時間)」が
どれだけ必要か考えましょう。
このように
興味関心のあるものに関連付けることで、
勉強嫌いを克服できます。
効果的な勉強法を知る
勉強をしても成績が伸びない方は、
効果的な勉強法を知ることで
一気に成績を伸ばせるかもしれません。
効果的な勉強法は多くあります。
そして、その勉強法が適しているかも
人それぞれ違います。
まずは、自分なりの勉強法を
見つけることが大切です。
いろんな勉強法を試し、
一番成績が上がる勉強法を
見つけましょう。
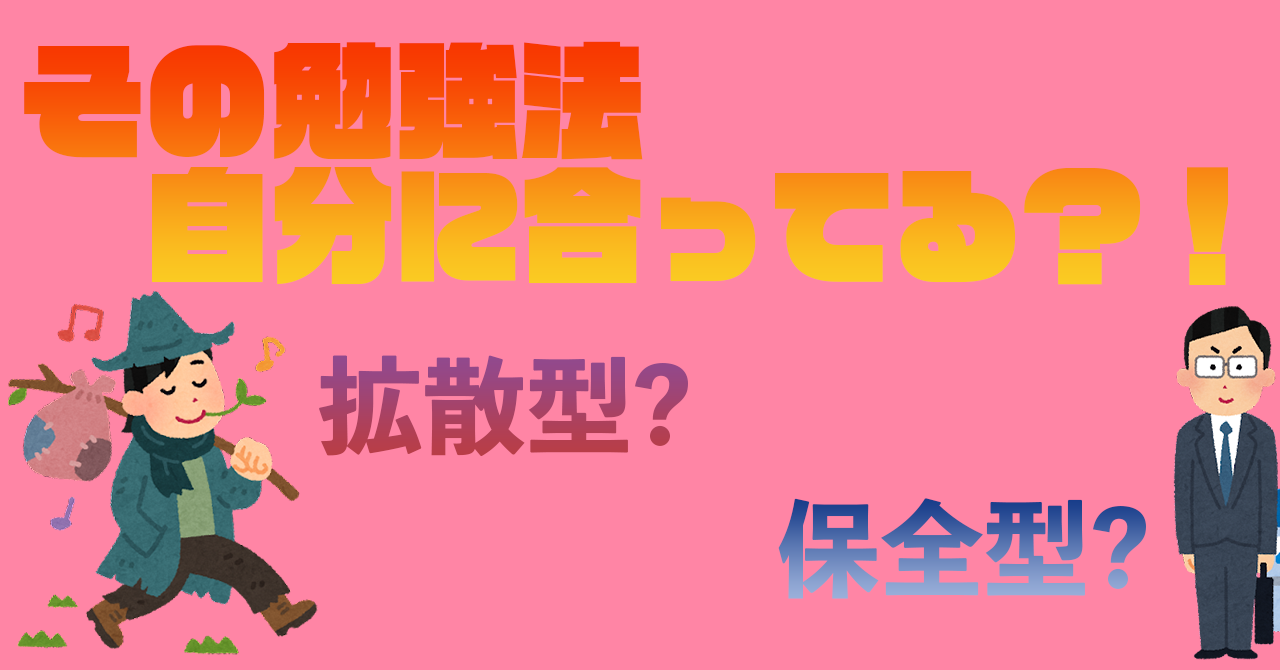
勉強して達成したい目標を設定する
目標がないと勉強する意味を見出せません。
無意味なことをやらされていると感じていれば、
勉強嫌いになるのも仕方ないでしょう。
目標を設定する際は、
- 最終目標
- 1ヶ月の目標
- 1週間の目標
というように
ここでもスモールステップで
目標を設定することがおすすめです。
例えば、
- 最終目標:定期テストで全教科80点以上
- 1ヶ月の目標:苦手な英語を強化
- 1週間の目標:テスト範囲の英単語を覚える
といったように
「最終目標」に必要な過程を
「1ヶ月の目標」
「1週間の目標」に設定します。
最終目標だけを設定していると、
どこかで中だるみしてしまうので
中間の目標も大切です。
「1週間の目標」を設定することで、
「最終目標」に近づけるとともに
達成感を味わえます。
勉強嫌いの子どもに対する良い接し方
勉強嫌いの子どもへのサポートは
発達段階によって異なります。
もちろん、その子の個性にもよるので、
子どものことを想像しながら
どの接し方が適しているのか判断してください。
小学生の子とは一緒に勉強する
子どもは親を見て育ちます。
親が率先して勉強していれば
「勉強しなさい」と言わなくても、
子どもは勉強する意識に変わります。
このとき、親は子どもと同じ勉強をする
必要はありません。
勉強することがなければ、読書でもOKです。
家事などで忙しいかと思いますが、
親自ら机に向かうことで、
子どもも「勉強しよう!」という気持ちになります。
中学生・高校生の子とは適切な距離を取る
中学生・高校生は多感な時期です。
親の言うことを素直に聞けないことも
多くなるでしょう。
そのため、あれこれ言い過ぎると
かえって子どもはやる気を無くす
恐れがあります。
しかし、親が口出しすることを辞めても、
子どもが自ら勉強するわけではありません。
むしろ、状況は悪化するでしょう。
ポイントは、親が適切なタイミングで
サポートすることです。
子どもが助けを求めているとき、
困っているときに
すっと手を差し伸べましょう。
勉強嫌いの子どもに対するNGな接し方
最後に、勉強嫌いの子どもに
してはいけない接し方をご紹介します。
NGな接し方は下記の主に下記の2つです。
- 「勉強しなさい」と言う
- スマホやゲームなどを取り上げる
「勉強しなさい」と言う
「勉強しなさい」とつい言いたくなりますよね。
しかし、「勉強しなさい」と声をかけることは
まったくの逆効果です。
これは、ブーメラン効果と呼ばれています。
ブーメラン効果とは、
相手を説得すればするほど、
説得内容とは逆の行動をしてしまうというもの。
また、「◯◯しなさい」
「◯◯したらダメ」
という命令を受けると、
逆の行動をしたくなるという効果もあります。
人間は自由を制限されると、
「自分には自由がある」
ということを確認するために
逆の行動を取る傾向があるのです。
スマホやゲームなどを取り上げる
勉強しない原因が
スマホやゲームなどの娯楽だった場合、
多くの保護者はその娯楽を取り上げることで
勉強に集中させようとします。
しかし、娯楽を取り上げてしまっても、
他の娯楽を求める傾向があります。
そのため、娯楽を取り上げても
効果は期待できません。
スマホやゲームなどの娯楽に依存している子は、
精神的な悩みを抱えていることが多い
と言われています。
学校での悩みや勉強の悩みなどから
逃げるために、娯楽に依存しているのです。
まずは、この悩みを解決しましょう。
悩みのタネはさまざまなので、
ここで解決策を提案することはできませんが、
スマホやゲームなどの娯楽を取り上げても、
問題は何も解決されないのでお気をつけください。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は「勉強嫌いの子ども」をテーマに
その原因や対策について解説しました。
「勉強嫌い」という性質は
生まれ持ったものではなく、
何らかの原因によって作り上げられたものです。
つまり、その原因を把握することが大切。
子どもとしっかりコミュニケーションを取り、
勉強嫌いの原因を確認して
次のステップに進みましょう!