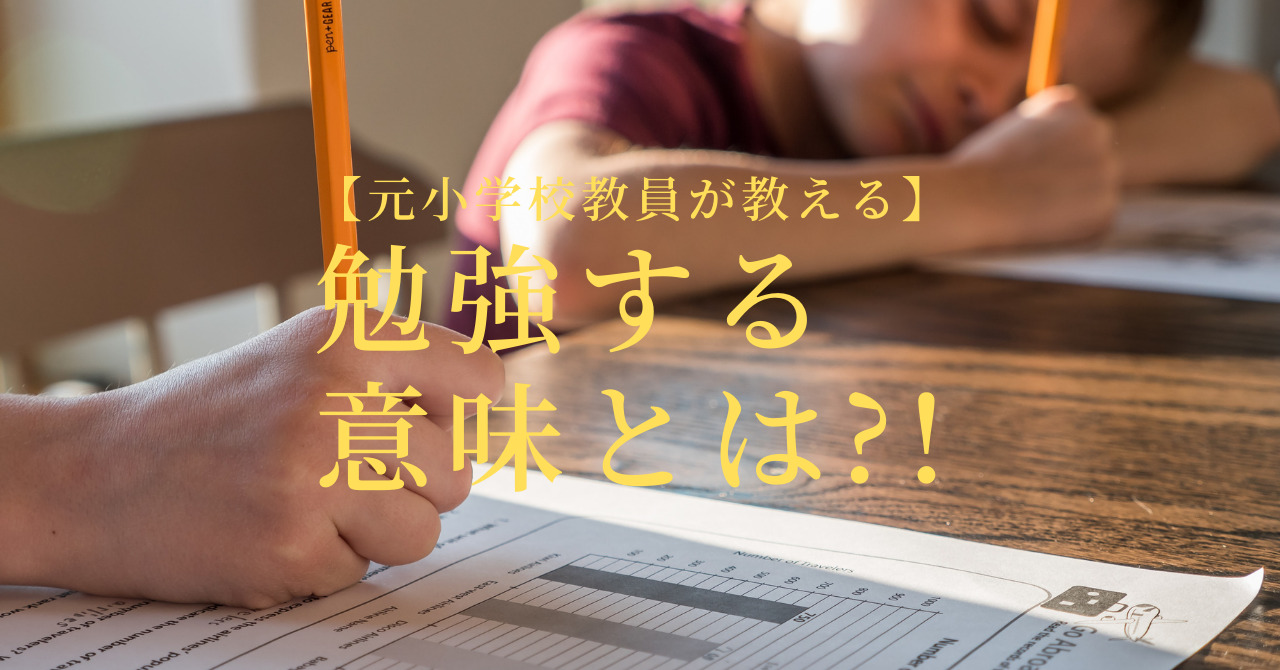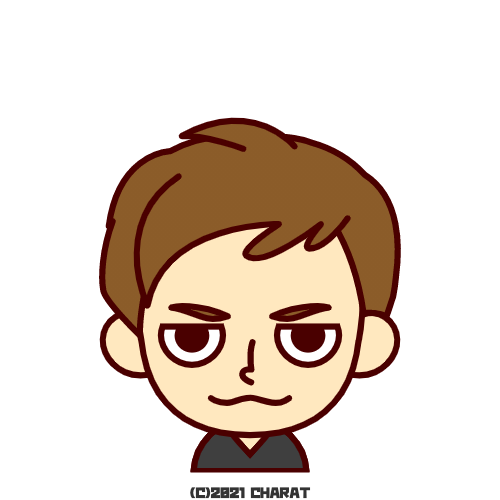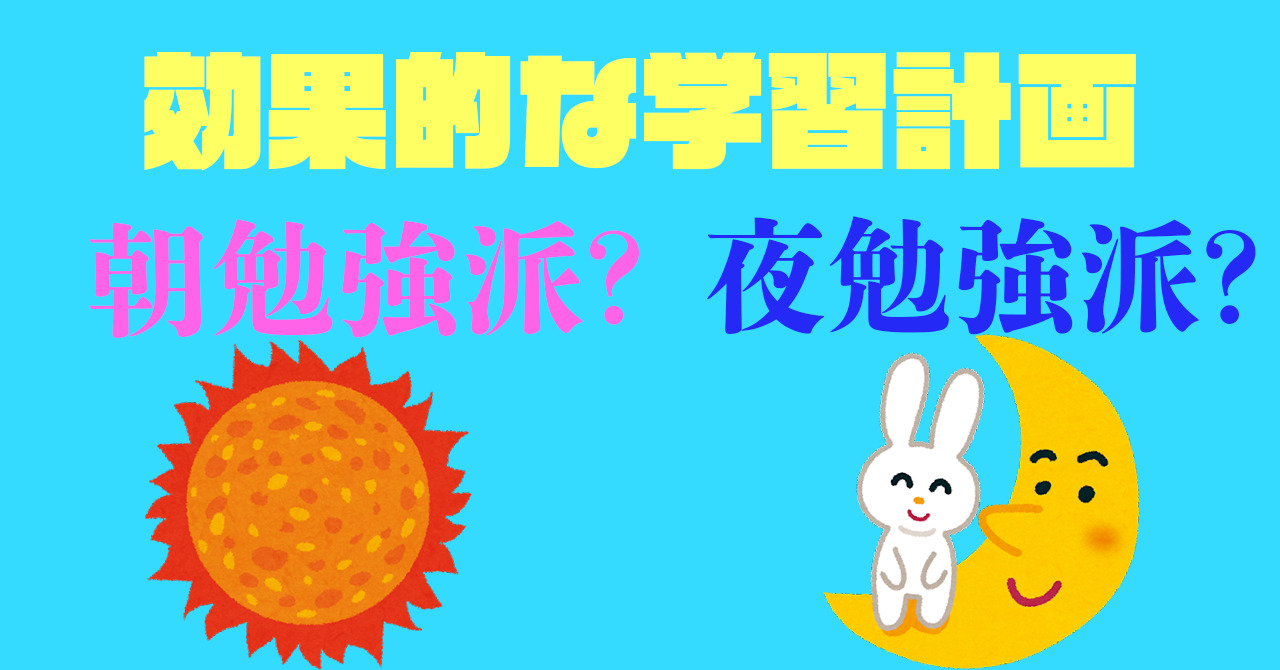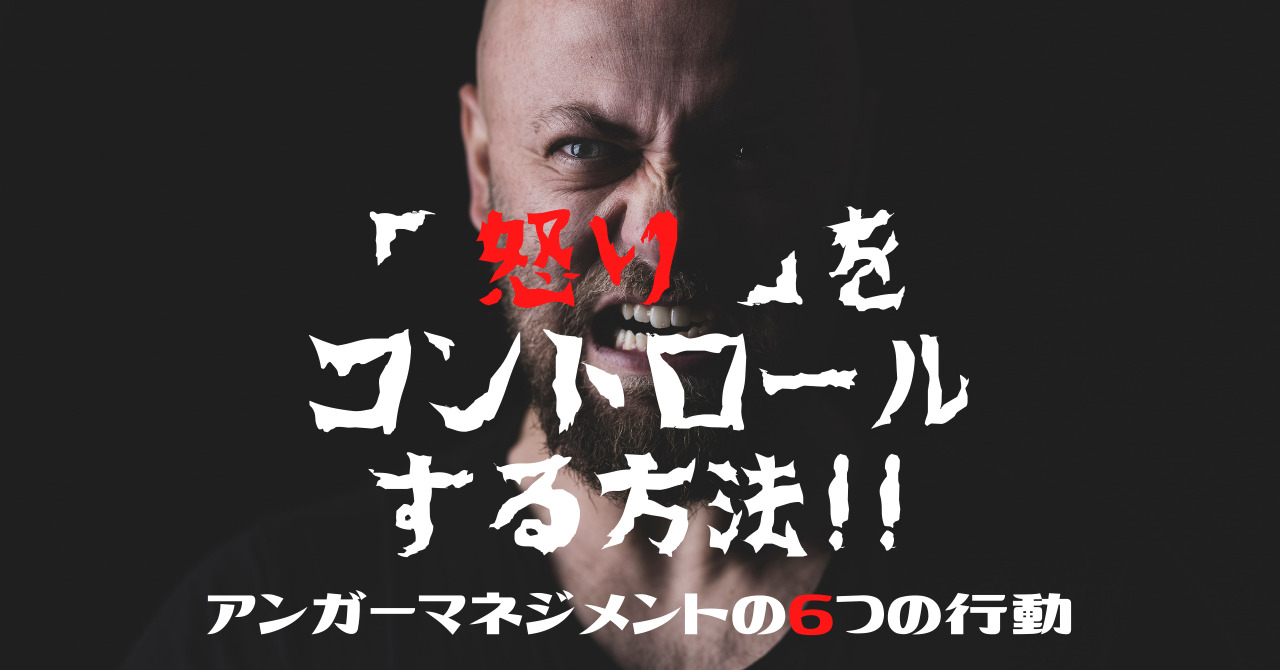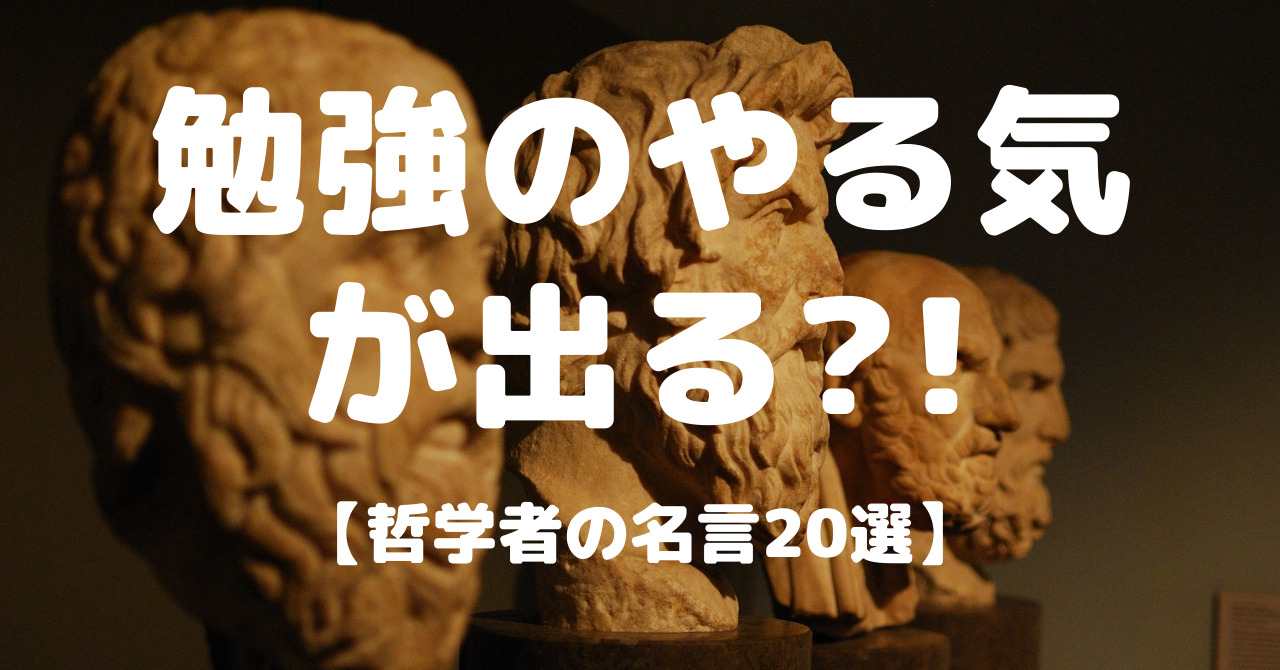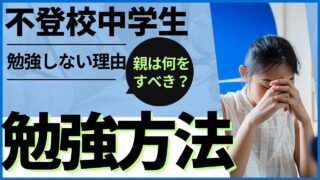「なんで勉強しないといけないの?」
と考えたことはありませんか?
本来勉強は楽しむものです。
しかし、勉強に嫌悪感を感じている方は
おおいでしょう。
そこでこの記事では、
勉強する意味について解説します。
勉強する意味を知ることで
勉強するやる気が出ますので、
ぜひ参考にしてください。
- 勉強する意味が分からない方
- 勉強を嫌だと感じてしまう方
- 勉強のやる気を上げたい方
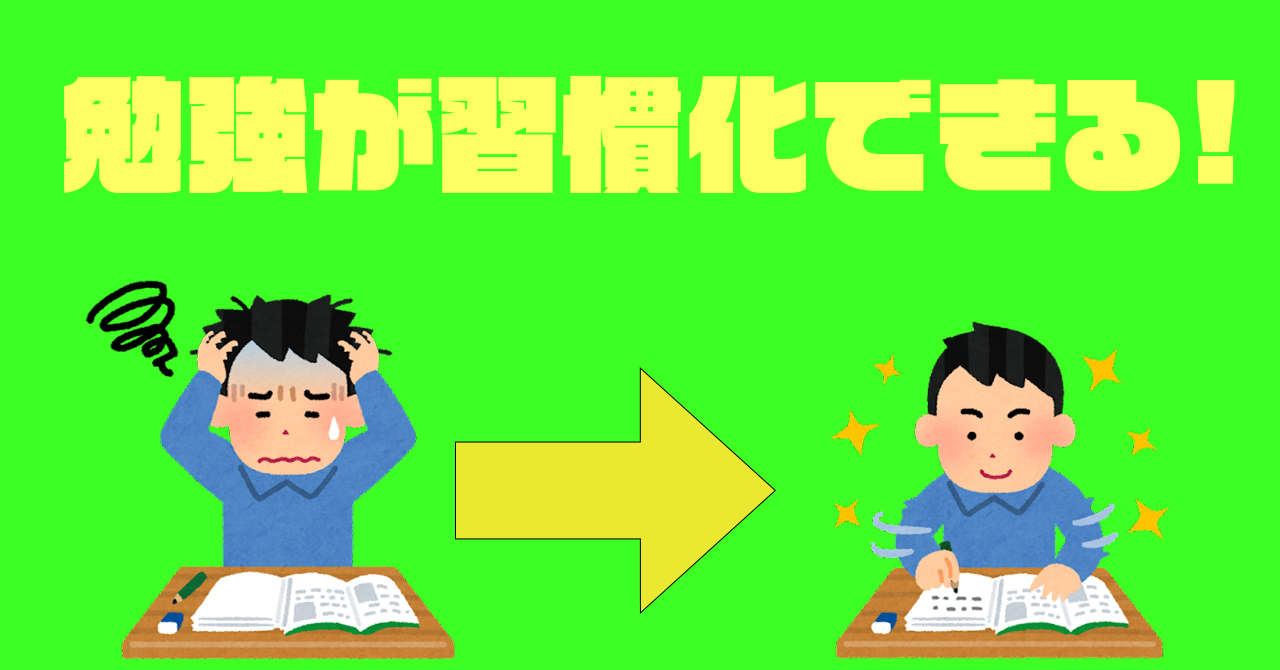
勉強する意味とは
勉強する意味は主に
下記の3つが挙げられます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
- 将来の選択肢が増える
- 過去に人類が努力して得た知識を一瞬で学べる
- 世界が広がる
1.将来の選択肢が増える
勉強することで将来の選択肢が増えます。
今現在の日本では、
ある程度の学力・学歴がなければ、
将来の選択肢は広がりません。
義務教育を経て高校、
大学に進まないと、
有名企業等に就職することは
かなり困難です。
実際、平成30年度の調査によると、
正社員雇用率は大学卒の79.1%に比べ、
中卒は11.7%とごくわずかとなっています。
もちろん中卒で経営者になった方も
いますが、それはごく一部を
メディアが取り上げているだけです。
つまり、しっかり勉強して
大学に進学しなければ
将来の選択肢は狭まってしまいます。

2.過去に人類が努力して得た知識を一瞬で学べる
2つ目は、長い期間を経て
積み重ねられた知識を
一瞬で学べるということです。
知識というものは、
人類が図ることができないほど
努力してできたもの。
例えば葉を見ても、
昔の人は呼吸や光合成をしている
などと考えていませんでした。
しかし、研究を重ね
葉緑体というものを発見したり、
葉が日光にあたり酸素を排出したり
していることが分かったのです。
この研究をするためにも、
様々な実験が繰り返されています。
そして、葉が呼吸や光合成をしていると
何十年、何百年とかけて
発見したのです。
このようなすごいことを、
教科書の1ページほどでわかるように、
今の勉強は簡単にされて受け継がれています。
3.世界が広がる
3つ目は、「世界が広がる」ことです。
例えば5歳程度の子どもにとって、
葉を見ても「もの」としか
捉えられません。
しかし、
小学校低学年の生活科で葉に触れ、
理科に進むと構造についても勉強し、
葉を「もの」から「葉」と捉え始めます。
「もの」としか捉えられなければ、
楽しいはずがありません。
知識をつけ見方が変わることで、
世界が広がります。
これは勉強しないとできないこと。
知識が増え、世界が広がると、
その分楽しめることも増えていきます。
勉強嫌いになる理由
勉強嫌いになる理由は人それぞれ。
ここでは、私が教員や塾長時代に
多くの子どもから聞いた
「勉強嫌いになった理由」を
3つご紹介します。
- 楽しくない
- 必要性を感じる内容が少ない
- 評価を気にしている
それぞれ詳しく見ていきましょう。
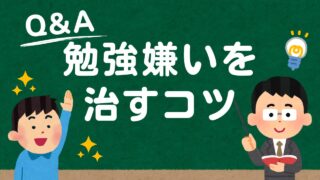
1.楽しくない
まず「勉強は楽しくない」です。
勉強すること、そして
新しい知識を身につけるということは、
とても素晴らしく楽しいことです。
しかし多くの子どもは
勉強を楽しく感じていません。
それは、
ただノートの漢字を書くだけであったり
淡々と計算をするだけであったりと
勉強が作業になっているからです。
新しい知識を身につけるよりも、
復習することが勉強になってしまうと
勉強はあまり楽しくありません。
もちろん復習も大切ですが
楽しさを感じるためにも
予習に力を入れてみてはいかがでしょうか。
2.必要性を感じない
2つ目は
「必要性を感じない」
ことです。
多くの子どもたちは
公立の学校で勉強しています。
しかし公立の学校教育では、
決められた学習内容を
行うことしかできません。
その勉強ほとんどは、
生活に結びつけることが困難です。
例えば国語で古典を勉強したとしても、
それが役に立つときは
滅多にありませんよね。
もちろん古典を勉強することにも
意味はあるのですが、
多くの子どもたちは理解できません。
そのため、勉強を必要と感じないのです。
3.評価を気にしている
3つ目は
「多くの子どもは評価を気にしている」
ことです。
多くの子どもは
成績・内申のために勉強しています。
ある先生は評価を書くそぶりをすると、
子どもたちが真面目になると
嬉しそうに話してたほどです。
評価の良し悪しは
さまざまな意見がありますが、
評価が目的になることは
絶対にあってはなりません。
しかし、実際は評価を武器に
大人は勉強させているように
なっているのも事実です。
もちろん成績も大事ですが、
あまり気にしすぎず、
勉強そのものを楽しみましょう。
大人が「勉強しろ」と言う理由
では、なぜ大人は
勉強させてくるのでしょうか。
それには、日本の
「偏差値重視の勉強」という
問題点が挙げられます。
「入試に合格する」
「偏差値が高い学校に入る」
ための教育が日本式です。
偏差値や有名大学のブランドを気にして、
そのゴールを目指すために
勉強させています。
実際日本の保護者や教員の多くは
子どもの志望校を選ぶ際、
その子どもの個性を見るのではなく、
偏差値を基準として学校選びを
しているでしょう。
また、テストで点数の高かった子が
「優秀な子」と考えられるため、
試験で高い点数を取るための教育を
大人が求めているのです。
勉強は本来楽しむもの!
日本の教育システムにより、
「評価」のために
勉強しがちになってしまっています。
しかし本来は
「楽しいを探究し続けるため」、
また「生きるため」に
勉強するものです。
常に新しい知識を得て、
学びの楽しさを感じてもらえると
幸いです。