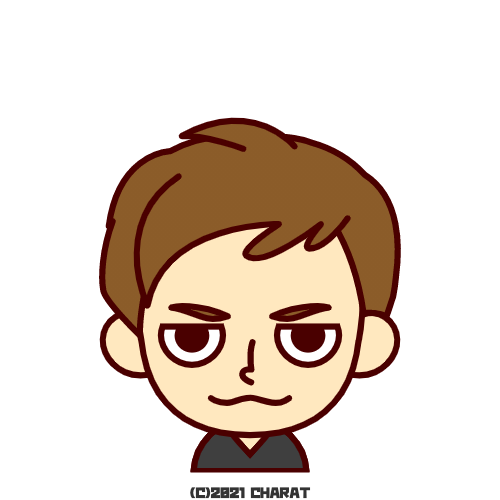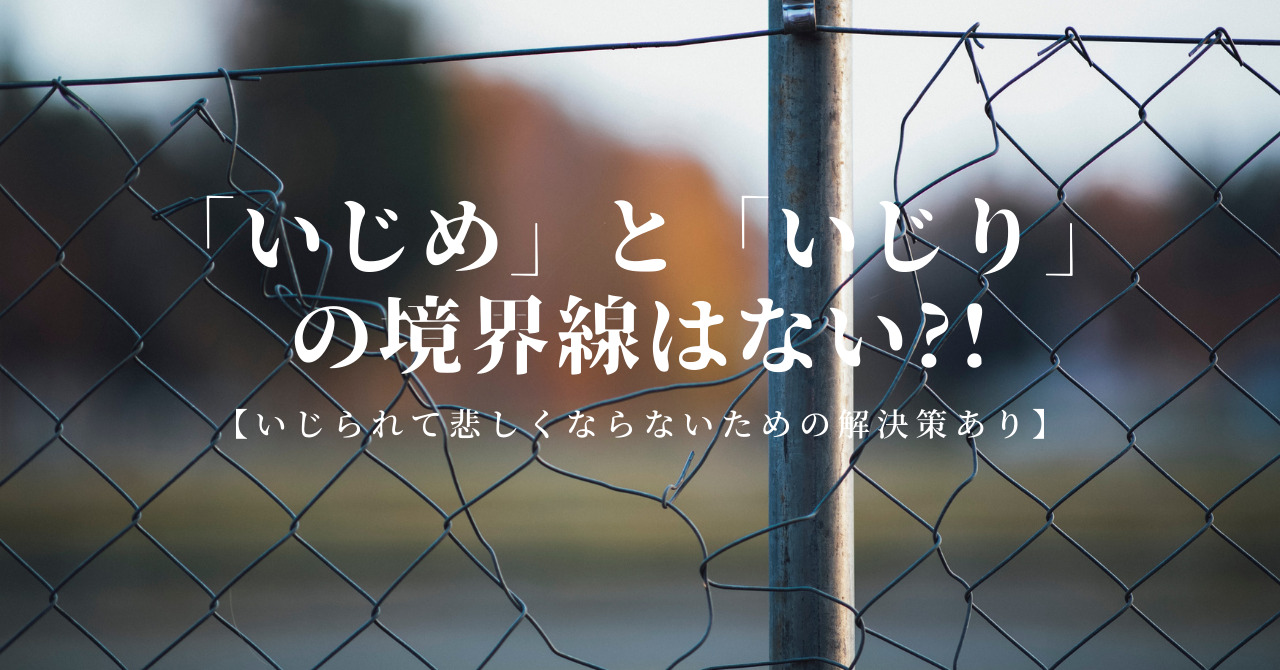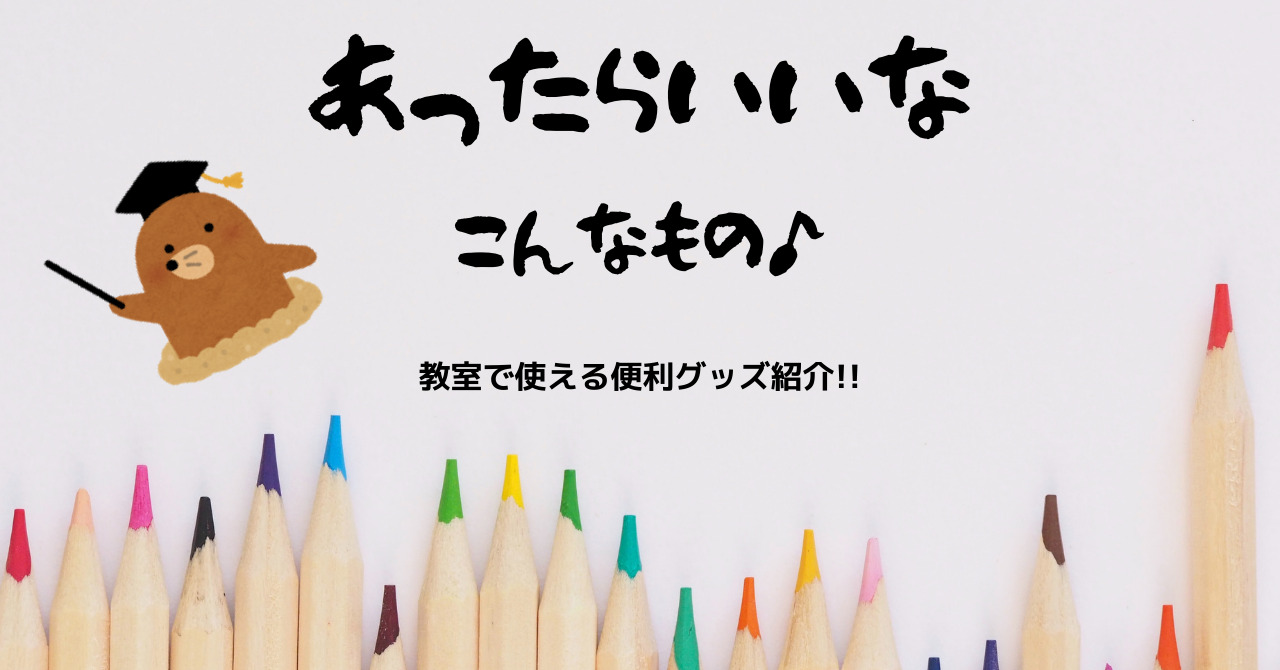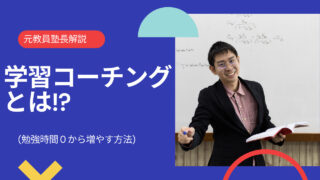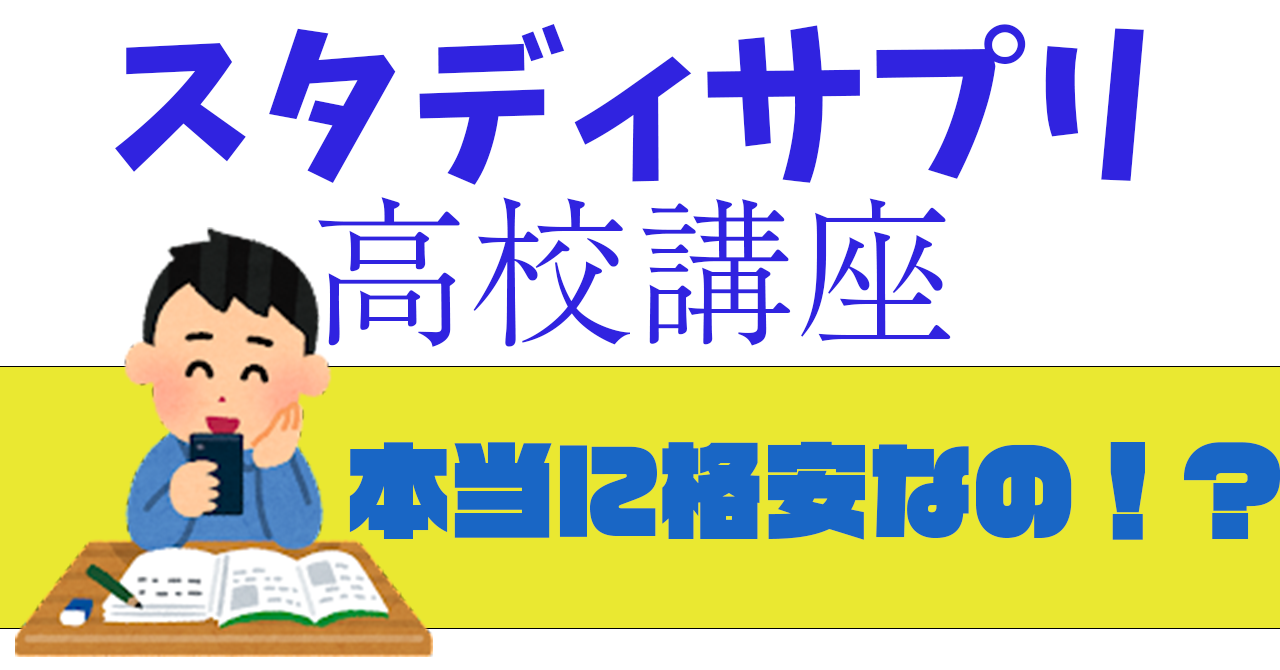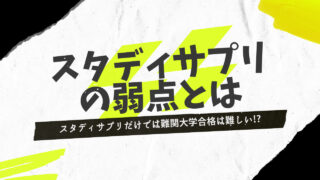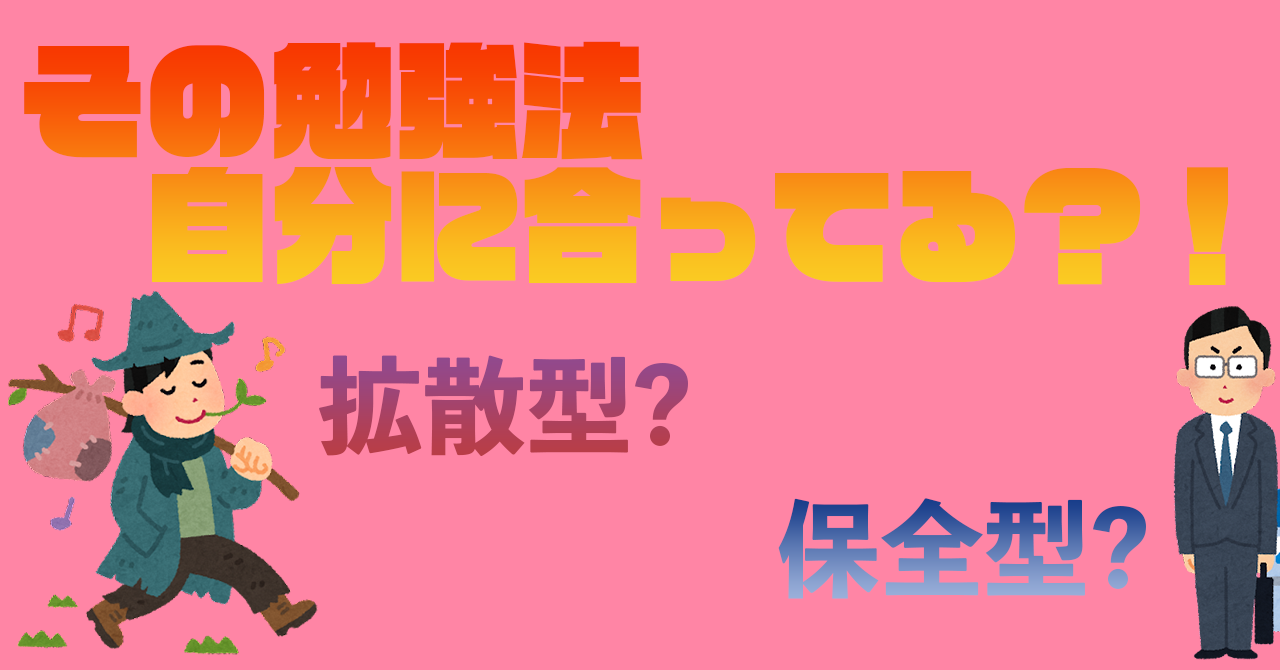あなたは教育の中でどのような力を育てることを求めていますか?
保護者の方、教員の方それぞれ一人ひとりに何か想いがあるでしょう。そんな中、これからの時代求められてくるものは「思考力」と「コミュニケーション能力」と言われていますよね。
しかし、この思考力とコミュニケーション能力ってどうやって育てるの?と思っている方は多くいるかと思います。そんなとき、効果的なのが「こども哲学」です。
こども哲学は、日常の当たり前に潜む素朴な疑問について、自由に考え自分の考えを話したり、人の考えを聞いたりする対話活動です。
そこでこの記事では、そんなこども哲学について解説していきます!
- 思考力・コミュニケーション能力を育てたい方
- 子ども哲学を取り入れたい方
子ども哲学とは
まず、哲学と聞くと「難しそう…」「無意味で役に立たない…」といったイメージを思い浮かべる方は多いでしょう。たしかに、専門的な哲学書は何を言っているのかわからないことがほとんどです。
しかし、ここでご紹介するこども哲学とは哲学対話と呼ばれる対話活動のことを言います。それは決して難しいものではなく、意外とシンプルで取り組みやすいものです。最近では、この哲学対話」を実践している先生方も増え、有名私立学校でも教科として導入されています
実際、私も教員時代自分のクラスで実践しましたが、哲学対話を実践することでクラスは大きく成長しました。
哲学対話は、答えがない問いについて探求する活動です。
例えば、「那覇市って何県にあるの?」とか「今の総理大臣は誰?」といった問いには答えがありますよね。
それに対して答えのない問いとは、「普通ってどういうこと?」とか「なんで勉強しなきゃいけないの?」といった問いになります。このように、答えのない問いは、人によって答えが違ってくるもので、正解はありません。それぞれの考えを伝え合いながらお互いの思考を深めていくことがこの哲学対話なのです。
哲学対話で得られるもの
哲学対話をすることによって、子どもは多くのものに気づき成長します。具体的に、下記のようなものを哲学対話を通して得られます。
- 自分の価値観に気づく
- 友達との違いに気づく
- 友達の意見を尊重して聞くようになる
- それぞれの考え方から、また別の考え方が生まれる
- 考えることの楽しさを知ることができる
これって、最初に言った「コミュニケーション能力」や「思考力」に当てはまりますよね。哲学対話をすることによって、これらを一気に得ることができるのです。
何よりも、「正解はない」つまり「間違いもない」というところに子どもたちは惹かれていました。「間違いがない」から積極的に考え、考えることの楽しさを見出すのです。
また、哲学対話は子どもだけでなく大人にもメリットがあります。子どもから、「これってどういうこと?」と聞かれるても、大人はついつい「今忙しいから後でね…」と子どもの疑問から目を背けてしまうことがありますよね。しかし、哲学対話によって大人は子どもの発言や考えを理解できるようになります。
哲学対話の実践事例紹介
では、哲学対話はどのように行うのでしょうか。
ここでは、実際に私が教員時代に行った手順を紹介します。
ステップ1:問いを作る
まずは、哲学対話するための問いを考えます。日々の生活の中に疑問を見出し、それを自分自身の力で形にするため、子どもたちで問いを作ってもらいます。
私は、日常の疑問を見落としてもらわないように、疑問があれば紙に書いて専用のボックスに入れてもらっていました。そして、そこから今回行う問いを決めるのです。
また、問いが見つからなかったときは、NHK for Schoolの「Q〜こどものための哲学」を教材として活用していました。
ステップ2:問いについて考え、質問し合う
次に、決まった問いについて自分の意見を考えます。そして、その意見を発表し合うのですが、このとき「自分の意見を主張し合う議論」ではなく、「問い合う」ことを重視する必要があります。
自分の意見を主張するだけでは、深まることはありません。他者の意見を聞き、その意見について質問します。さらに、意見を伝える側も質問されることでより自分の意見が深まります。
また、哲学における質問とは、相手を詰問・尋問するためのものではなく、相手の考えをよく理解して自分の考えを深めるためのものであることが大事です。この際、私のクラスでは4〜5人の小グループに分かれて行っていました。
ステップ3:みんなで話し合う
最後に、ステップ2で作られた小グループごとに行った話し合いの内容をクラス全体で共有します。その際、私のクラスはみんなでサークルになって行いました。
また、全体の際にはファシリテーターを決め進行してもらっていました。教員の仕事は、議論がテーマからハズレすぎないように見守ることです。それまで、沈黙にも耐えて子ども自身から発言が出てくるのを待ちましょう。
その代わり、教員は議論の哲学的深まりのキーとなる発言に注目し、その発言との関連において質問や発言を促すことによって問いを哲学的に深めていきましょう。
哲学対話をするときの注意事項
哲学対話をする際、最も気をつけなければならないのが「安心して参加できているか」です。
哲学対話は相手を言いまかすのではなくいろいろな考えを認めることを重視してください。そのために、哲学対話を始める前に、ルールを決めておきましょう。私のクラスのルールを載せておくので参考にしてください。
- 友達が話している時は最後まで聞く
- 誰かが傷つく発言はNG
- 何も言わなくていいが、考えることはやめない
- 友達の言っていることがわからなければ、質問をする
- 最終的に一つの結論が出なくてもOK
まとめ
最後までご覧いただき、ありがとうございます。「子ども哲学」についてわかったでしょうか。
思考力、コミュニケーション能力を一気に得ることができる子ども哲学は今後必須となるでしょう。
参考になりましたら、ぜひ実践してみてください。